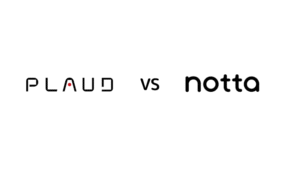AIボイスレコーダーとして便利なPLAUD NOTEをさらに活用したいと考えたとき、「PLAUD NOTEで複数アカウントは使えるのだろうか?」あるいは「一台のデバイスを家族や同僚とデバイス共有できたら便利なのに」といった疑問をお持ちになるかもしれませんね。
仕事とプライベートでデータを分けたいけれどアカウント共有の可否はどうなのか、その場合のデータ同期やクラウド連携の仕組み、さらにはアカウント切り替えのスムーズさなど、気になる点は多いことでしょう。
この記事では、PLAUD NOTEにおける複数アカウントの利用に関するこれらの疑問点を解消し、現状でどのような使い方ができるのか、またどのような点に注意すべきかを詳しく解説していきます。
- PLAUD NOTEでの複数アカウント作成の可否と実用上の制約
- 一台のデバイスを複数人でアカウント共有する際の具体的な注意点
- 複数のPLAUD NOTEデバイスを単一アカウントで管理する方法と利点
- 現状の製品仕様における最適なアカウントの利用方法とデータ整理のコツ
PLAUD NOTEの複数アカウント利用について
- 複数アカウントは作成できる?
- PLAUD NOTEでのデバイス共有はできるのか
- 1台のPLAUD NOTEをアカウント共有する注意点
- 複数デバイスを1アカウントで管理する方法
- 仕事と個人用でアカウントを分けたい場合
複数アカウントは作成できる?
PLAUD NOTEで複数のアカウントを作成すること自体は、技術的には行えます。具体的には、アカウントごとに異なるメールアドレスを用意することで、システム上は別々のアカウントとして登録することが可能です。
しかしながら、実用面を考えるといくつかの注意点があります。例えば、スマートフォンアプリには、異なるアカウントを簡単に切り替えるための機能が現状搭載されていません。
そのため、別のアカウントを利用したい場合は、一度ログアウトしてから再度別のアカウント情報でログインし直すという手間が発生します。
さらに、AIメンバーシップの特典、例えば月間の無料文字起こし時間や特定の機能へのアクセス権などは、アカウントごとに独立して管理されます。
つまり、あるアカウントで購入したプランや特典を、別のアカウントに移行したり共有したりすることはできません。
仕事用とプライベート用で完全にデータを分けたい、といった目的で複数アカウントを運用しようとすると、これらの点が不便に感じる場面が出てくるでしょう。
PLAUD NOTEでのデバイス共有はできるのか
一台のPLAUD NOTEデバイスを、家族やチームのメンバーなど複数の人が、それぞれ自身の個別アカウントで共有して利用することは、現在の製品仕様では想定されていません。
原則として、一台のPLAUD NOTE本体は、特定の時点では一つのPLAUDアカウントにのみ紐付けて使用する設計になっています。
これを別の角度から見ますと、例えば、一台のパソコンを複数のユーザーアカウントで切り替えて使うような形での利用はできない、ということです。
もし、あるPLAUD NOTEを別のアカウントで使用したいと考えた場合、まず現在紐付いているアカウントからデバイスの登録を解除する手続きが必要です。
その上で、新しく利用したいアカウントで再度デバイスを紐付ける作業を行うことになります。
この切り替え作業は手軽とは言えず、また、デバイスをアカウントから解除すると、そのアカウントに紐付いていたデバイス内の録音データなどが削除される点にも留意しなくてはなりません。
そのため、複数人で一台を柔軟に使い分けたいというニーズには、現状では応えにくい状況です。
1台のPLAUD NOTEをアカウント共有する注意点
前述の通り、1台のPLAUD NOTEを複数人で利用する場合、それぞれの個人アカウントで使うことはできません。
結果として、誰か一人のアカウントを事実上の共有アカウントとして使う形になりますが、これにはいくつかの重要な注意点が存在します。
最も大きな点は、プライバシーの管理でしょう。デバイスに記録される全ての録音データは、その単一の共有アカウントに集約されます。
そのため、個人のプライベートな会話や機密情報を含む会議の内容も、アカウントにアクセスできる人であれば誰でも聞けてしまう可能性があります。
誰の録音データなのか、後から判別しにくいという整理上の問題も出てくるかもしれません。

また、AIメンバーシップの特典についても考慮が必要です。月間の無料文字起こし時間などの上限があるサービスは、共有アカウントのメンバー全員で分け合って利用することになります。
もし一人が集中的に利用した場合、他の人が必要な時に特典を利用できないという事態も起こりえます。
データを誤って削除してしまうリスクや、誰がどのデータを利用しているかの把握が難しくなる点も、運用上の課題と言えるでしょう。
複数デバイスを1アカウントで管理する方法
PLAUD NOTEは、複数のデバイスをお持ちの場合でも、それらを一つのアカウントで効率的に管理できる仕組みを提供しています。
参照:複数のPLAUD NOTEを同一アカウントで登録できますか?
例えば、ご自宅用と職場用、あるいは持ち運び用といった形で複数のPLAUD NOTEデバイスを所有していても、すべて同じご自身のPLAUDアカウントに紐付けることが可能です。
新しいデバイスをアカウントに追加する手順は、基本的に最初のデバイスを登録した際と同じです。
こうして複数のデバイスを一つのアカウントに登録しておけば、どのデバイスで録音したデータであっても、自動的にそのアカウントに集約され、同期が行われます。これにより、データの一元管理が非常にスムーズになります。
ただし、スマートフォンアプリに同時にアクティブに接続できるPLAUD NOTEデバイスは、一度に一台のみという点には注意が必要です。
複数のデバイスがアカウントに紐付いている場合、アプリ内の「私のPLAUDデバイス」といったメニューから、現在アクティブに接続するデバイスを選択し、切り替える操作を行います。
この切り替え作業自体は、アプリ内で比較的簡単に行えるようになっています。この方法の利点は、一つのAIメンバーシップ(サブスクリプション)で、所有する全てのデバイスからの録音データを管理できる点にあります。
仕事と個人用でアカウントを分けたい場合
仕事関連の録音と、プライベートな内容の録音を明確に分けて管理したいというニーズは多くの方がお持ちでしょう。PLAUD NOTEでこれを実現する方法としては、いくつかの考え方があります。
まず、技術的には、仕事用と個人用にそれぞれ異なるメールアドレスを使用して、完全に別々のアカウントを作成すること自体はできます。しかし、この方法は実用的とは言い難い側面があります。
なぜなら、PLAUD NOTEのアプリには、複数のアカウントを簡単に切り替える機能が備わっていないためです。
そのため、アカウントを使い分けるには、その都度アプリからログアウトし、別のアカウント情報で再ログインするという手間が発生します。
加えて、AIメンバーシップの特典やサブスクリプションもアカウントごとに独立しているため、それぞれのアカウントで契約が必要となり、費用も二重にかかる可能性があります。
そのため、より現実的な対応策としては、一つのPLAUDアカウントを運用し、その中でデータを整理・区別する方法が推奨されます。
例えば、仕事用と個人用にPLAUD NOTEデバイスを2台用意し、両方を同じアカウントに紐付けます。2台目をPLAUD NotePinにするのもおすすめです。

録音データは一つのアカウントに集約されますが、PLAUD Web(パソコンのブラウザからアクセスできるサービス)のフォルダ機能を活用し、「仕事用」「個人用」といったフォルダを作成してデータを分類することが可能です。
あるいは、録音時のファイル名に識別しやすいキーワード(例:「会議_20250515」「趣味_日記」など)を付けるといった運用ルールを設けることでも、データの区別はつきやすくなるでしょう。
PLAUD NOTE 複数アカウント運用のポイントとデータ管理
- アプリでのアカウント切り替え機能の現状
- スムーズなデータ同期の仕組みとは
- クラウド連携で複数端末からアクセス
- 複数アカウント利用時のサブスクリプション
- 複数アカウントより推奨される使い方
アプリでのアカウント切り替え機能の現状
PLAUD NOTEのスマートフォンアプリにおいて、複数のアカウントをお持ちの場合でも、それらを素早く簡単に切り替えるための専用機能は、残念ながら現在のところ提供されていません。
もし異なるメールアドレスを使用して複数のPLAUDアカウントを作成・所有しているユーザーが、別のアカウントに保存されているデータを確認したり、別のアカウントでサービスを利用したりしたい場合、一度現在ログイン中のアカウントからログアウトする必要があります。
その後、改めて利用したいアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインし直す、という手順を踏まなくてはなりません。
例えば、仕事用アカウントと個人用アカウントを分けている方が、SNSアプリのようにプロフィールアイコンをタップして瞬時にアカウントを切り替える、といった利便性の高い操作は行えないのが実情です。
そのため、頻繁にアカウントを使い分けたいというニーズをお持ちの方にとっては、この点が少々手間だと感じられるかもしれません。
スムーズなデータ同期の仕組みとは
PLAUD NOTEで録音された音声データは、主にBluetooth通信を利用して、お使いのスマートフォンアプリへとスムーズに同期されるように設計されています。
録音が完了すると、PLAUD NOTE本体とペアリング設定されているスマートフォンアプリとの間でデータの転送が開始されます。
具体的には、PLAUD NOTEデバイスとスマートフォンがBluetoothで接続されていれば、録音データはアプリ内のストレージに保存されます。
これにより、録音した音声をアプリで再生したり、文字起こしや要約といったAI機能を利用したりできるようになります。
一部の情報では、より大容量のデータを高速に転送するためのWi-Fi転送モードについても言及されていますが、日常的な多くのケースではBluetoothによる同期が基本となるでしょう。
さらに、アプリに同期されたデータは、「PLAUD Private Cloud」というクラウドサービスを通じて、インターネット上に安全にバックアップすることも可能です。
このクラウド同期機能を有効にしておくことで、スマートフォンを買い替えた際や、万が一紛失してしまった場合でも、新しい端末で同じアカウントにログインすれば、過去の録音データに再びアクセスできるようになります。
クラウド連携で複数端末からアクセス
前述のデータ同期とPLAUD Private Cloudの機能を活用することで、PLAUD NOTEで作成・管理している録音データや文字起こし結果などに、複数の異なる端末からアクセスすることが可能になります。
例えば、外出中にPLAUD NOTEで録音し、スマートフォンのアプリへ同期したデータを、帰宅後やオフィスでパソコンの大きな画面で確認・編集したい場合があると思います。
このような時、パソコンのウェブブラウザからPLAUD Web(app.plaud.aiというアドレスの専用ウェブサイト)にアクセスし、お持ちのPLAUDアカウントでログインします。
すると、スマートフォンアプリで見ているのと同じデータが一覧表示され、パソコンからでも内容の確認、編集、整理といった作業が行えます。
このクラウド連携によって、スマートフォンだけでなく、タブレットやパソコンなど、状況に応じて最適なデバイスを選んでデータを利用できる柔軟性が生まれます。
なお、セキュリティの観点からか、新しい端末でアカウントにログインした際に、それまで使用していた別の端末でのログインセッションが自動的に終了(ログアウト)される場合がある点にはご留意ください。
しかし、データそのものはクラウド上に安全に保管されていますので、再度ログインすれば問題なくアクセスできます。
複数アカウント利用時のサブスクリプション
PLAUD NOTEで複数のアカウントを運用する場合、AI機能の利用に関わるサブスクリプション(AIメンバーシップなど)の扱いは特に注意が必要です。
基本的に、これらの有料プランやそれに付随する特典は、お申し込み手続きを行った特定の一つのPLAUDアカウントに対して紐付けられます。
具体的に申しますと、例えば高精度な文字起こしサービスの時間制限や、クラウドストレージの容量拡張といったメンバーシップ特典は、アカウントごとに独立して管理されることになります。
もし、仕事用と個人用など、目的別に複数のアカウントを作成し、それぞれのアカウントでAI機能をフル活用したいと考えた場合、原則としてアカウントの数だけ個別にサブスクリプション契約が必要になる可能性があります。
あるアカウントで購入したプランの特典を、別のアカウントに移行したり、複数アカウント間で特典を合算して利用したりすることはできません。
このため、複数のアカウントを維持するには、それぞれに費用が発生することを理解しておく必要があります。これは、複数アカウント運用を検討する際の経済的な負担に関わる重要なポイントと言えるでしょう。
複数アカウントより推奨される使い方
ここまでご説明してきたように、PLAUD NOTEで複数のアカウントを個別に作成し運用するには、アカウント切り替えの手間やサブスクリプションの管理など、いくつかのハードルが存在します。
そのため、多くの場合、一つのアカウントを最大限に活用する方法が推奨されます。
特に、仕事の記録と個人の趣味の録音を分けたい、あるいは異なるプロジェクトごとにデータを整理したいといったニーズに対しては、無理にアカウントを分けるよりも、単一のアカウント内でデータを工夫して管理・整理する方が、結果として利便性が高く、スムーズな運用につながることが多いです。
具体的な方法としては、まず、もし物理的に録音環境を分けたいのであれば、複数のPLAUD NOTEデバイス(例えば、仕事専用機とプライベート専用機)を用意し、それらを全て同じ一つのPLAUDアカウントに紐付けるという手段があります。
こうすることで、データは一元的に同じアカウントに集約され、AIメンバーシップも一つで済みます。
録音データの区別については、PLAUD Webのフォルダ機能を活用し、「業務関連」「個人的な記録」といった形で分類したり、ファイル名に一貫したルール(例:「会議20250515プロジェクトA」「趣味アイデアメモ〇〇」など)を設けて管理したりすることで、効率的に整理することが可能です。
この方法であれば、アカウント管理の煩雑さや追加の費用負担を避けつつ、実質的な使い分けが実現できるでしょう。
PLAUD NOTEにおける複数アカウント運用の要点
- PLAUD NOTEで複数アカウント作成は異なるメールアドレスで技術的に可能だ
- アプリに複数アカウントの簡易切り替え機能はない
- AIメンバーシップ特典はアカウント間で移行や共有ができない
- 1台のデバイスを複数アカウントで共有利用することはできない
- デバイスの紐付けアカウント変更には再設定とデータ削除が伴う
- 1アカウントを複数人で使う場合プライバシー確保が難しい
- 1つのアカウントに複数のPLAUD NOTEデバイスを紐付けられる
- 複数デバイスのデータは1アカウントに集約され一元管理できる
- 仕事用と個人用は1アカウント内で整理するのが現実的だ
- データは主にBluetooth経由でスマホアプリに同期される
- PLAUD Private Cloudでデータはクラウドにも同期・保管される
- クラウド連携によりPCなど複数端末からデータアクセスが可能だ
- 複数アカウントでAI機能をフル活用する場合サブスクリプション費用が個別に発生しうる
- メーカーは1アカウントを工夫して活用する方法を推奨している
- 複数デバイス利用時もAIメンバーシップは1つで済む場合が多い