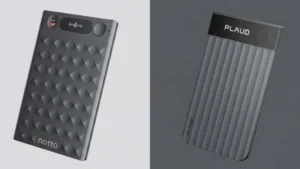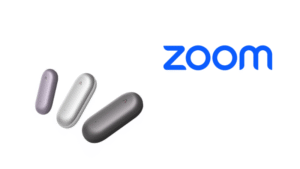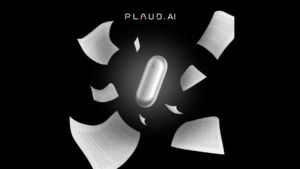手軽に音声を記録し、AIが自動で文字起こしや要約を行ってくれるウェアラブルデバイス、PLAUD NotePin。
その画期的な機能に注目が集まる一方で、「セキュリティは本当に信頼できるのか」と不安を感じている方も少なくないでしょう。
そもそも、PLAUD NotePinとはどのような製品なのか、開発している企業はどこの国に拠点を置いているのか。そして、録音したデータはどこに保存されるのか。
情報漏洩といったリスクはないのかといった点は、実際に利用するうえで非常に重要な関心事です。
また、セキュリティ面の懸念に加え、文字起こしの精度に対する不満や、無料プランで利用できる機能の制限、PC接続に対応していない点、Web版の使い勝手など、機能面や利便性についての疑問もよく聞かれます。
この記事では、PLAUD NotePinのセキュリティに関するさまざまな疑問や懸念について、製品の仕組みやデータ管理の実態、公式な説明、そして利用者の評判などをもとに、多角的に解説していきます。
安心して使えるかどうか、ご自身の利用スタイルに合っているかを判断するための参考になれば幸いです。
- PLAUD NotePinの製品概要とデータ管理の仕組み(クラウド依存、PC接続不可等)
- PLAUD社が講じるセキュリティ対策(暗号化、SOC 2認証)とその信頼性
- 情報漏洩リスクやプライバシーに関する懸念点、利用上の注意点
- 文字起こし精度や無料プランの制限など機能面の評価と実態
PLAUD NotePinのセキュリティは平気なのか?基本解説
- そもそもPLAUD NotePinとはどんな製品?
- 開発元はどこの国?製造国との関係性
- データはどこに保存される?クラウド利用の実態
- 文字起こし精度は?「使えない」という声も
- 無料プランでできることは?制限と内容
- PLAUD NOTEとNotePinの違い:機能とセキュリティ
そもそもPLAUD NotePinとはどんな製品?
PLAUD NotePinは、指でつまめるほど小型・軽量なウェアラブル型AIボイスレコーダーです。日常の会話やふとしたアイデアを「メモリーカプセル」として手軽に記録することをコンセプトに開発されています。
このデバイスの主な魅力は、シンプルな操作性と、AIによる高度な情報整理機能にあります。
本体中央のボタンをワンタッチするだけで録音を開始・終了でき、特別な設定や操作は必要ありません。録音データはBluetooth経由でスマートフォンの専用アプリに転送されます。
転送された音声は、GPT-4oやClaude 3.5 Sonnetといった高性能AIにより自動で文字起こしや要約が行われます。112言語に対応しており、多言語環境での利用も視野に入れられています。
会議やインタビュー、講義、移動中のアイデア記録など、さまざまなシーンで活用でき、記録や情報整理の手間を大幅に軽減できるのが特徴です。
ただし、いくつか注意点もあります。先行モデルのPLAUD NOTEに搭載されていた、スマートフォンの通話を高音質で録音できるVCS(骨伝導センサー)や、USB接続によるPCとのデータ連携機能は、PLAUD NotePinには搭載されていません。
データ管理は基本的にスマートフォンアプリとクラウドに依存する形となるため、この点は事前に理解しておく必要があります。
開発元はどこの国?製造国との関係性
PLAUD NotePinを開発・販売しているのは、アメリカ・ワイオミング州に登記されたNicebuild LLCという企業です。2021年に設立され、ボイスレコーダーをはじめとするハードウェアおよび関連ソフトウェアの開発を手がけています。
日本市場向けには「PLAUD Japan」という日本法人を設立し、渋谷にオフィスを構えるなど、日本での展開にも力を入れていることがうかがえます。
なお、製品の製造自体は中国で行われていると明記されており、開発とブランド運営をアメリカ、製造を中国が担う分業体制が採られています。
録音データやAIによる処理後のデータは、主にアメリカ国内にあるGoogle CloudやAWSといった大手クラウドサービス上に保存されると説明されています。

つまり、PLAUD NotePinは「アメリカの企業が開発・運営し、中国で製造され、データはアメリカのクラウドに保存される」という構成になっています。
こうした国をまたぐ体制は、製品の国際的なスケールを示す一方で、セキュリティやデータ管理に関して懸念を抱くユーザーも一定数存在します。
とくに、国外からのアクセス可能性やプライバシーへの影響を不安視する声もあるため、「アメリカ企業の製品」という一言では語りきれない背景を理解しておくことが重要です。
データはどこに保存される?クラウド利用の実態
PLAUD NotePinで録音した音声データは、複数の段階を経て保存される仕組みになっています。まず、録音された音声はデバイス本体の64GBメモリに一時的に保存されます。
その後、Bluetooth接続を通じてスマートフォンの専用アプリ「PLAUD App」へデータが転送されます。転送が完了すると、デバイス本体から音声データは自動的に削除される仕様です。
これは、万が一デバイスを紛失した際に、第三者に録音内容を聞かれるリスクを軽減するためと考えられます。
アプリに取り込まれたデータは、ユーザーの設定により「PLAUD PRIVATE CLOUD」と呼ばれるクラウド同期機能を使って、インターネット上のサーバーへ保存することができます。
この機能を有効にすると、音声データだけでなく、AIが生成した文字起こしや要約もクラウドにアップロードされます。
PLAUD社によれば、クラウド保存にはGoogle Cloud、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azureなどの信頼性の高いサービスが使われており、サーバーの所在地は主にアメリカ国内とされています。
また、クラウドのストレージ容量は「無制限」と案内されており、容量不足の心配はほとんどありません。
クラウド同期を利用することで、スマートフォンのアプリだけでなく、PCのWebブラウザからもデータにアクセスできるようになります。
ただし、PLAUD NotePinはパソコンとUSBケーブルで直接接続してデータを取り出す機能を備えていません。そのため、録音データの管理はアプリおよびクラウドサービスの利用が前提となります。
ローカル環境のみでデータを管理したいユーザーにとっては、この点が不便に感じられるかもしれません。
文字起こし精度は?「使えない」という声も
PLAUD NotePinのAIによる文字起こし精度については、ユーザーからさまざまな評価が寄せられています。静かな環境で、はっきりと話された音声であれば、比較的高い精度で文字起こしされるようです。
実際、多くのレビューでは「多少の修正は必要だが、概ね満足できる」「要約機能と組み合わせると非常に便利」といった肯定的な意見が見られます。
個人的なメモや、内容が比較的シンプルな会議記録であれば、十分に実用的と感じるユーザーが多いようです。

一方で、評価が分かれる要因として、特定の環境や条件下での精度低下が挙げられます。
たとえば、騒がしい場所での録音、複数人が同時に話す会話、専門用語を多く含む議論などでは、文字起こしの精度が大きく落ちるという指摘があります。
具体的には、「話者の区別ができない」「誤字や脱字が多く、議事録としてそのまま使えない」「ノイズキャンセリングが弱い、または強くすると音声が途切れる」といった声が寄せられています。
満足のいく結果を得るには、静かな環境で録音することが重要といえるでしょう。
このように、PLAUD NotePinの文字起こし機能が「使える」と感じるか「使えない」と感じるかは、使用する環境や内容、そしてユーザーが求める精度の水準によって大きく異なります。
導入を検討する際は、実際の利用シーンを想定しつつ、レビューなどを参考に慎重に判断することをおすすめします。

無料プランでできることは?制限と内容
PLAUD NotePinを購入すると、特別な申し込みをしなくてもAI機能を利用できる無料プラン「AIスタータープラン」が付属します。このプランでは、録音した音声の文字起こしや要約といった基本的な機能を試すことができます。
ただし、無料プランにはいくつかの制限があります。最も重要なのは、AIによる文字起こし時間に上限がある点です。多くの情報によれば、無料プランでは月あたり最大300分(約5時間)までしか文字起こしを利用できません。
たとえば、短時間の打ち合わせメモや思いついたアイデアの記録といった用途であれば、この範囲内でも十分に使える可能性があります。
しかし、会議を頻繁に録音したい場合や、インタビューなどで日常的に文字起こしを活用したい場合は、月300分ではすぐに上限に達してしまうでしょう。
この制限を超えて文字起こしを使いたい場合や、録音内容についてAIに質問できる「Ask AI」などの高度な機能を利用したい場合には、有料のサブスクリプションプラン(プロプラン、無制限プランなど)への加入が必要です。

たとえばプロプランでは、月1,200分(20時間)まで文字起こしが可能になり、年間で約12,000円の費用がかかります(※料金は変更される可能性があります)。
このように、PLAUD NotePinでは無料プランで基本機能を体験できますが、頻繁に使う場合やより高度な機能を求める場合は、有料プランの利用が実質的に必要になるケースも多いでしょう。
自分の利用頻度や目的に合わせて、適切なプランを選ぶことが大切です。
PLAUD NOTEとNotePinの違い:機能とセキュリティ

PLAUD NotePinは、以前に発売された「PLAUD NOTE」の後継機ではなく、異なるコンセプトに基づいた新しい製品ラインです。
そのため、両者には機能や設計思想、さらにはセキュリティやデータ管理の方法において、いくつか重要な違いがあります。
まず、本体のデザインと携帯性が大きく異なります。NotePinは、ピンやクリップで衣服に装着できるカプセル型デザインを採用しており、重量は約16.6gと非常に軽量です。
一方、NOTEは名刺サイズの薄型カード型で、重量は約30gでした。
機能面では、NOTEの特徴であったVCS(骨伝導センサー)によるスマートフォン通話の高音質録音機能が、NotePinには搭載されていません。
また、録音モード(通話/通常)を切り替える物理スイッチもNotePinにはなく、主に対面での会話や周囲の音の録音に特化した仕様となっています。
バッテリーの持続時間も異なり、NotePinは約20時間、NOTEは約30時間の連続録音が可能です。

セキュリティやデータ管理の面で最も大きな違いは、パソコンとの接続方法です。PLAUD NOTEはUSBケーブルでパソコンに直接接続し、録音データをコピーしたり、外部ストレージとして扱うことができました。
一方、NotePinはUSB経由でのデータ転送には対応していません。
NotePinの録音データは、Bluetooth経由でスマートフォンの専用アプリに転送され、必要に応じてクラウドに同期される仕組みです。
パソコンでデータを確認・利用したい場合は、クラウド同期を有効にし、「PLAUD Web」と呼ばれるWebブラウザ経由のインターフェースを使う必要があります。
この仕様変更により、NotePinはスマートフォンアプリとクラウドサービスへの依存度が高くなっています。
そのため、オフラインでのデータ管理や、ファイルをPCで直接扱いたいユーザーにとっては、従来のNOTEの方が柔軟性が高かったと感じられるかもしれません。
気になるPLAUD NotePinのセキュリティと使い方
- 情報漏洩のリスクは?暗号化はされている?
- 注意!NotePinはPC接続ができない仕様
- Web版の使い方は?PCでのデータ活用
- SOC 2認証・HIPAA準拠の信頼性
- プライバシーポリシーで確認すべき点
- まとめ:セキュリティを重視するなら?
情報漏洩のリスクは?暗号化はされている?
PLAUD NotePinを利用するうえで、録音データなどの情報漏洩リスクは多くのユーザーにとって気になるポイントです。PLAUD社は、こうした懸念に対し、複数のセキュリティ対策を講じていると説明しています。
具体的には、データがスマートフォンアプリからクラウドサーバーに送信される際や、クラウド上で保存される際に暗号化が施されているとしています。
「エンドツーエンドでの暗号化」を採用し、通信経路全体が保護されていることを強調。また、セキュリティ管理体制の信頼性を示す国際的な認証「SOC 2 Type II」を取得していることも、安全性の裏付けとしてアピールされています。
さらに、デバイス本体に保存された録音データは、スマートフォンのアプリに転送されると自動的に削除される仕様になっており、万が一デバイスを紛失しても、そこから情報が漏洩するリスクは抑えられています。
とはいえ、リスクがゼロというわけではありません。たとえば、ユーザー自身のPLAUDアカウントのパスワードが脆弱だったり、他のサービスと使い回していたりすると、不正アクセスのリスクが高まります。
また、PLAUDのシステムやアプリに未知の脆弱性が存在する可能性も完全には否定できません。
加えて、文字起こしや要約の処理にはOpenAIやAnthropic(Claude)といった外部のAIサービスが使われており、匿名化されたうえで音声データがそれらのサービスに送信される仕組みになっています。
この際のデータの取り扱いについても、第三者サービス側のセキュリティ方針に依存する面があるため、一定のリスクを伴います。
PLAUD社は暗号化の導入を明言していますが、具体的にどの暗号化技術を使っているのか、鍵の管理方法はどうなっているのかといった技術的な詳細は公開されておらず、ユーザーがその強度を客観的に判断するのは難しいのが現状です。
このように、PLAUD NotePinには一定水準のセキュリティ対策が施されていますが、クラウドサービスや外部AIとの連携を前提とした仕組みである以上、潜在的なリスクは完全には排除できません。
利用者自身によるアカウント管理の徹底や、情報の取り扱いに対するリスク意識を持つこともあわせて重要となります。
注意!NotePinはPC接続ができない仕様
PLAUD NotePinを検討している方が特に注意すべき点のひとつが、パソコンとUSBケーブルで直接接続して録音データを取り出すことができないという仕様です。
以前のモデルである「PLAUD NOTE」では、USBケーブルでPCに接続するとUSBメモリのように認識され、録音された音声ファイル(WAV形式など)を直接コピー・管理することが可能でした。
音声編集ソフトで加工したり、ローカルでバックアップしたりする際に便利な機能でした。
しかし、PLAUD NotePinに搭載されているUSB Type-Cポートは充電専用となっており、PCに接続してもストレージデバイスとしては認識されません。
このため、録音データをパソコンで確認・利用するには、以下のような手順を取る必要があります。
- BluetoothでPLAUD NotePinとスマートフォンを接続する。
- 専用の「PLAUD App」を使い、NotePin本体からアプリへデータを転送する(転送後、本体データは削除)。
- (PCで利用したい場合) アプリの設定で「クラウド同期」を有効にする。
- パソコンのWebブラウザから「PLAUD Web」にアクセスし、同期されたデータを確認・利用する。
この仕様には、USB接続を介したウイルス感染などのリスクを避けられるというメリットもありますが、多くのユーザーにとっては不便に感じられる可能性が高いでしょう。

特に、「クラウドにはデータを保存せず、自分のパソコンだけでオフライン管理したい」といったニーズには対応できません。
実際、録音データの管理方法はスマートフォンの専用アプリと、事実上推奨されているクラウドサービスに限定されており、ユーザー側で柔軟な運用を行うことは難しくなっています。
こうしたデータアクセスの制限は、PLAUD NotePinを選ぶ際の重要な判断材料の一つになります。自分の運用スタイルやセキュリティ方針と合っているかどうかを、購入前にしっかりと検討しておくことが大切です。
Web版の使い方は?PCでのデータ活用
PLAUD NotePinはパソコンに直接接続してデータを取り出すことはできませんが、録音データやAIによる文字起こし・要約結果をパソコンで確認・活用したい場合には、「PLAUD Web」と呼ばれるWeb版インターフェースが利用できます。

これを使えば、スマートフォンアプリとほぼ同様の機能をパソコンのブラウザ上でも操作することが可能です。Web版を利用するための基本的な手順は以下の通りです。
- まず、お使いのパソコンでChromeやEdge、SafariなどのWebブラウザを起動します。
- アドレスバーに
app.plaud.aiと入力してアクセスします。 - ログイン画面が表示されるので、普段スマートフォンアプリで利用しているPLAUDアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
- ログインに成功すると、クラウドに同期されている録音データの一覧や、それぞれの文字起こしテキスト、要約などが表示されます。
PLAUD Webでは、音声データの再生、文字起こしテキストの編集、キーワードによる検索、テキストデータのエクスポート(コピー&ペーストやファイル出力)などが可能です。
特に、AIが生成するマインドマップ形式の要約などは、スマートフォンの小さな画面よりもパソコンの広い画面で確認したほうが、全体の構造を把握しやすく、より実用的でしょう。
ただし、Web版を利用するためには、ひとつ重要な前提条件があります。それは、スマートフォンのPLAUDアプリで「クラウド同期」機能をあらかじめ有効にしておく必要があるという点です。
クラウド同期が無効のままだと、Web版にログインしても録音データや文字起こし結果は表示されません。
つまり、パソコンでデータを活用したい場合には、一度PLAUD社のクラウドサーバーにデータをアップロードする必要があります。この仕様を理解したうえで、Web版の機能を活用することをおすすめします。
SOC 2認証・HIPAA準拠の信頼性
PLAUD社は、自社サービスの安全性を示す根拠として「SOC 2 Type II認証」の取得と「HIPAA準拠」をアピールしています。これらは、特にセキュリティを重視する法人ユーザーや医療関係者にとって重要な判断材料となるでしょう。
まず、SOC 2 Type II認証とは、外部の監査機関が企業の情報セキュリティ体制について、データ保護、可用性、処理の完全性、機密保持、プライバシー保護といった観点から、一定期間にわたり継続的に適切な運用が行われていることを確認・証明するものです。
PLAUD社がこの認証を取得していることは、セキュリティ対策に真剣に取り組んでいる姿勢を示すものであり、一定の信頼性を担保する材料になります。
また、HIPAA準拠とは、米国の医療情報保護法(Health Insurance Portability and Accountability Act)に基づいた基準を満たしていることを意味します。
患者のプライバシーや医療データの保護に関する要件をクリアしているため、PLAUD社は医師と患者の会話記録といった医療現場での利用も想定していると考えられます。
ただし、こうした認証や準拠の表明が、PLAUD NotePinの利用におけるすべてのセキュリティリスクを排除するわけではない点には注意が必要です。
第1に、SOC 2やHIPAAはPLAUD社自身のシステムや運用体制に関する評価であり、文字起こしや要約に使用される外部AIサービス(OpenAIやClaudeなど)が同等の基準を満たしているかどうかまでは含まれていません。
また、ユーザー自身によるパスワード管理の不備(弱いパスワードや使い回しなど)によるリスクも対象外です。
第2に、HIPAA準拠が示されていても、実際に医療情報(PHI)を扱う場合は、PLAUD社と利用者(病院や医療機関など)との間で「ビジネス・アソシエイト契約(BAA)」を結ぶ必要があるケースもあります。
準拠の具体的な適用範囲や条件については、事前に確認しておくことが重要です。
このように、SOC 2認証やHIPAA準拠はPLAUD社の信頼性を測るうえで有益な指標ではあるものの、それだけで「絶対に安全」と判断するのは適切ではありません。
自分の利用目的やデータの性質を踏まえ、サービス全体の構造と潜在的なリスクを総合的に見極めることが大切です。
プライバシーポリシーで確認すべき点
PLAUD NotePinのようなデバイスを利用する際は、提供されている「プライバシーポリシー」に目を通しておくことが非常に重要です。
そこには、あなたの個人情報や録音データがどのように収集・利用・共有されるのかについての規定が記載されています。まず確認すべきは、「どのような情報が収集されるのか」という点です。
アカウント作成時に入力する氏名や連絡先に加え、デバイスの識別子、アプリの操作履歴、使用時間といった情報が、サービスの改善や機能向上を目的として収集される場合があります。
次に注目したいのは、「収集された情報がどのように利用され、誰と共有される可能性があるか」ということです。
サービス提供に必要な範囲での利用はもちろんのこと、提携企業や業務委託先、そして文字起こし・要約機能を提供する外部AIサービス(OpenAIやClaudeなど)とデータが共有される可能性があります。
PLAUD社はこれらのデータを匿名化したうえで提供するとしていますが、どの情報が、どの程度の匿名化処理を経て共有されるのかについて、明確に理解するのは容易ではないこともあります。
また、録音データや関連情報が主にアメリカ国内のサーバーに保存・転送される点にも注意が必要です。
これは、日本に住むユーザーにとっては「国際的なデータ転送」にあたるため、その際にどのような保護措置が講じられているのかも確認しておきましょう。
欧州のGDPR(一般データ保護規則)など、地域ごとに異なるユーザーの権利についての記載があるかもチェックポイントです。
加えて、「ユーザーが持つ権利」についても理解しておくことが重要です。
たとえば、自分のデータにアクセスする権利、誤りを訂正する権利、削除を要求する権利、そして第三者へのデータ提供を拒否する(オプトアウト)権利などが、ポリシー内でどのように保障されているかを確認しておきましょう。
プライバシーポリシーは法律文書の性質を持つため、少々読みづらいと感じる部分もあるかもしれません。
しかし、自分のデータがどのように扱われるのかを理解し、納得したうえでサービスを利用するためにも、とくに「データの共有範囲」と「ユーザーの権利」に関する記述は注意深く確認することをおすすめします。
まとめ:セキュリティを重視するなら?
PLAUD NotePinは非常に便利なデバイスですが、その構造上、セキュリティやプライバシーを重視する方にとっては、慎重な判断が必要になる場面もあります。
もし安全性を最優先に考える場合は、以下の点に注意しながら利用を検討することをおすすめします。まず、どのような情報を録音するかを意識することが重要です。
企業の機密情報、顧客との会話、個人的な相談内容など、万が一漏洩した場合に影響が大きい内容を扱う場合には、録音データをクラウドにアップロードしたり、外部のAIサービスに送信したりすることのリスクをよく検討する必要があります。
場合によっては、PLAUD NotePin自体が適していないという結論に至る可能性もあります。
次に、録音は必要な場面と内容に限定する「データ最小化」の考え方を意識してください。無関係な会話や周囲の雑音まで含めて記録してしまうと、不要なリスクが増えることになります。
また、他人の会話を録音する際には、事前に明確な同意を得ることが大前提です。これはマナーであると同時に、法的なトラブルを避けるためにも欠かせない行動です。
アカウントの管理も非常に重要です。パスワードは他のサービスと重複しないものを使用し、できるだけ複雑な内容に設定しましょう。
定期的な変更も推奨されます。セキュリティ強化のために、利用可能であれば二段階認証なども併用してください。
クラウド同期機能については、アプリの設定で有効または無効を選ぶことができます。Web版の活用やバックアップの面では非常に便利ですが、録音データをクラウドに置きたくないという方は、同期をオフにする選択肢もあります。
ただし、その場合は一部の機能が制限されることを理解しておく必要があります。
PLAUD NotePinはUSBケーブルによるパソコンとの直接接続に対応していません。そのため、録音データを完全にオフラインで管理したい方にとっては不便と感じられるかもしれません。
もし、ローカルでのファイル操作や管理を重視するのであれば、旧モデルのPLAUD NOTE(現在入手可能かは要確認)や、インターネット接続を前提としない従来型のICレコーダーを検討することも一つの方法です。
また、医療分野での利用を考えている場合には、PLAUD社が公表しているHIPAA準拠の内容や、ビジネスアソシエイト契約(BAA)の必要性などについて、事前に詳細を確認し、所属する組織のガイドラインに従って判断することが求められます。
これらのポイントを踏まえたうえで、ご自身の利用目的やリスクへの許容度に応じて、PLAUD NotePinを導入すべきかどうか、また導入後にどのような使い方をするかを冷静に判断することが大切です。
PLAUD NotePinセキュリティの重要ポイントまとめ
- PLAUD NotePinは小型軽量のウェアラブルAIボイスレコーダーである
- ワンタッチ録音とAIによる文字起こし・要約が主な機能だ
- 開発は米国企業Nicebuild LLCだが製造は中国で行われる
- データはアプリ転送後にクラウド(主に米国)へ保存、本体からは削除される
- クラウド同期は任意だがWeb版利用やバックアップに必要となる
- 文字起こし精度は環境や内容により変動、「使えない」との声もある
- 無料プランでは月300分の文字起こし時間制限がある
- 本格的な利用には有料プラン加入が実質的に必要となる場合が多い
- 旧モデルNoteとは異なりスマホ通話録音機能(VCS)はない
- NotePin最大の注意点はPCへのUSB直接接続が不可な点である
- データ管理はスマホアプリとクラウドサービスに強く依存する構造だ
- 情報漏洩対策として暗号化やSOC 2 Type II認証取得を主張する
- ただし暗号化の技術的詳細や第三者AI連携リスクには留意が必要だ
- プライバシーポリシーでデータ収集・共有範囲の確認が推奨される
- セキュリティ重視ならリスク評価と対策、代替案検討も視野に入れるべきだ