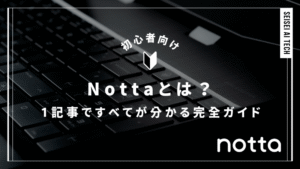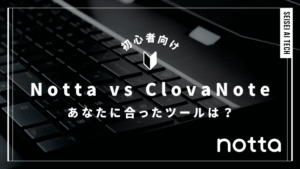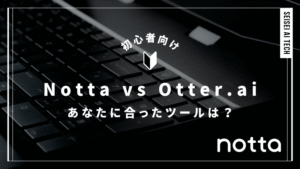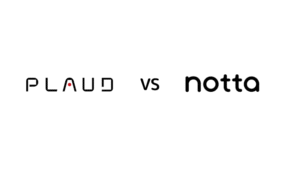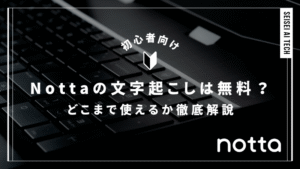近年、AIを活用した文字起こしサービスが注目を集めていますが、その中でも「Notta」の利用を検討している方も多いのではないでしょうか。
便利なツールである一方、「Nottaの安全性は大丈夫だろうか?」「情報漏洩の危険性はないのか?」といった疑問や不安を感じることもあるでしょう。
この記事では、Nottaのセキュリティについて、運営会社や開発された国といった背景情報も踏まえながら、詳しく解説していきます。
また、ツールの正確性についても触れつつ、安心して利用するためのセキュリティチェックシートのような視点も提供します。
Nottaの導入を考えている方、あるいはすでに利用していてセキュリティについて再確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
- Nottaの安全性と情報漏洩の潜在的な危険性
- Nottaの運営会社と開発された国
- Nottaが講じている具体的なセキュリティ対策
- Nottaの文字起こし機能の正確性
Nottaの安全性は?セキュリティ体制を徹底解説
- Nottaの運営会社と提供国はどこ?
- Nottaの文字起こしの正確性
- Nottaの基本的なセキュリティ対策
- 国際認証で見るNottaのセキュリティ
- セキュリティチェックシートの入手方法
Nottaの運営会社と提供国はどこ?
Nottaは、日本国内と海外の複数の法人が連携して運営しているサービスです。
具体的には、日本のユーザー向けには「Notta株式会社」がサービスの提供やサポートを担っています。この会社は東京の渋谷にオフィスを構え、2022年に設立されました。
一方、グローバルな視点で見ると、「Notta Inc.」という企業が英語の利用規約などで運営会社として記載されており、国際的な事業展開の中心を担っていると推測できます。
さらに、NottaのChrome拡張機能は「Airgram Inc.」というアメリカの企業が提供元となっており、以前Nottaと統合された経緯があります。
また、スマートフォンアプリは「MindCruiser」という名義で提供されていることも確認できます。このように、複数の企業がそれぞれの役割を分担してNottaのサービスを支えている構造です。
提供国・地域については、58言語もの文字起こしに対応していることから、日本を含む非常に広範な国々での利用が想定されていることが分かります。
Nottaの文字起こしの正確性
Nottaの文字起こしの正確性については、サービス提供側が最大で98.86%という高い数値を公表しています。これは、特にクリアな音声であれば、非常に信頼性の高いテキスト化が期待できることを示しています。
多くのユーザーにとって、文字起こしツールを選ぶ上で精度は最も重要な要素の一つでしょう。
例えば、1時間分の音声データであれば、約5分という短時間で文字起こしが完了するとされており、迅速な処理能力も特徴です。対応言語の幅広さも注目すべき点で、日本語や英語を含む58言語の文字起こしに対応しています。
さらに、文字起こしされたテキストを42の言語へ翻訳する機能も備わっているため、国際的な会議や多言語コンテンツを扱う際にも役立ちます。
ただし、音声の品質や話者の滑舌、周囲の騒音など、様々な要因が精度に影響を与える可能性も考慮しておく必要があります。

Nottaの基本的なセキュリティ対策
Nottaでは、ユーザーデータの安全性を確保するために、多層的なセキュリティ対策を講じていると説明されています。
まず、ユーザーとNottaのサーバー間の通信は、SSL/TLSという技術を用いて暗号化されています。これにより、データが送受信される過程での盗聴や改ざんのリスクを低減させています。
さらに、Nottaのサーバーに保存されるデータ自体も、AES-256という強力な暗号化方式で保護されているとのことです。
これは業界標準の暗号化技術であり、万が一不正アクセスがあった場合でも、データの内容を読み取られにくくするための重要な対策と言えます。
インフラには、高い信頼性を持つAmazon Web Services (AWS) を利用している点も、セキュリティ基盤の堅牢性につながる要素でしょう。
これらの基本的な対策に加えて、定期的な脆弱性診断や侵入テストなども実施しているとされています。
国際認証で見るNottaのセキュリティ
Nottaは、そのセキュリティ体制の信頼性を客観的に示すために、いくつかの国際的な認証を取得し、主要なデータ保護規制への準拠を表明しています。
これらは、Nottaが情報セキュリティに対して組織的かつ継続的な取り組みを行っていることを示すもので、利用者にとって安心材料の一つとなり得ます。
例えば、Nottaは2023年に「SOC 2 Type II認証」を取得しています。これは、セキュリティやプライバシーに関する組織の内部統制が効果的に運用されていることを第三者機関が証明するものです。
また、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO 27001認証」も同じく2023年に取得しました。
この他にも、EUの一般データ保護規則(GDPR)やカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)、そして日本の個人情報保護法(APPI)への準拠も表明しており、グローバルなデータ保護基準への対応意識がうかがえます。
これらの認証や準拠状況は、特にセキュリティ要件の厳しい企業がサービスを選定する上で、重要な判断基準となるでしょう。
セキュリティチェックシートの入手方法
企業がクラウドサービスを導入する際、そのセキュリティ対策の詳細を把握するために「セキュリティチェックシート」の提出を求めることが一般的です。
Nottaでは、日本国内の企業ユーザー向けに、このセキュリティチェックシートを提供しています。この取り組みは、日本の商習慣を理解し、国内企業が安心してサービスを検討できるようにするための配慮と言えるでしょう。
具体的に入手する方法としては、Nottaの公式ウェブサイト上に設けられた専用のフォームからリクエストする形になります。フォームに必要事項を入力して送信すると、シートのダウンロードリンクが提供される流れです。
提供されるシートは、日本の経済産業省が発行するガイドラインに準拠した形式で作成されていると説明されており、国内企業の評価基準に合わせた内容となっています。
ただし、この標準的なシートではカバーしきれない個別の質問への回答や、企業独自のフォーマットでの対応を希望する場合には、有料となるケースもあるようです。
また、第三者のクラウドサービスリスク評価プラットフォーム「Assured」を通じても、Nottaのセキュリティ情報をリクエストできると案内されています。
Nottaの安全性と注意すべき情報漏洩リスク
- Nottaの情報漏洩リスクとプライバシー保護
- Notta利用における危険性とは?
- AI学習へのデータ利用とユーザーの権利
- 過去のセキュリティインシデントは?
- Notta導入前に確認すべきこと
Nottaの情報漏洩リスクとプライバシー保護
Nottaを利用する際、アップロードした音声データや文字起こしされたテキストなどの情報がどのように扱われるのか、そして情報漏洩のリスクはどの程度あるのかは、多くの方が気になるところでしょう。
Nottaは、ユーザーのプライバシー保護とデータセキュリティを重視していると表明しており、そのための対策を講じていると説明しています。
具体的には、Nottaはサービス提供のために、ユーザーが登録したアカウント情報やアップロードしたコンテンツデータ、サービスの利用状況といった情報を収集します。
これらの情報は、アカウント管理、サービス提供・改善、カスタマーサポート、そしてセキュリティ向上といった目的で利用されるとのことです。
原則として、ユーザーの同意なしに個人情報が第三者に提供されることはないとされていますが、業務を委託するサービスプロバイダー(クラウドストレージ事業者や決済代行業者など)に必要な範囲で情報を提供する場合や、法令に基づく要請があった場合などは例外となります。
この際、委託先とは契約によって個人情報の保護を義務付けているとされています。
ただし、Nottaのプライバシーポリシーには、収集した情報を日本国外の事業者を含む第三者に提供する可能性がある旨も記載されており、この点は認識しておくべき事項です。
Notta利用における危険性とは?
Nottaは便利なAI文字起こしサービスですが、利用する上でいくつかの注意すべき点、あるいは潜在的な「危険性」として認識され得る側面も存在します。
これらを事前に理解しておくことは、安心してサービスを利用するために重要です。
まず一つは、前述の通り、自身のデータがどのように取り扱われるかという点、特にAIの学習に利用される可能性についてです。
機密性の高い情報を扱う場合、そのデータがAIモデルの改善・学習に用いられることに懸念を抱く方もいらっしゃるでしょう。
また、Nottaの運営には国内外の複数の法人が関わっており、契約主体やデータ管理の最終的な責任の所在が、利用者にとってやや分かりにくい構造になっている可能性も指摘できます。
さらに、一般的なクラウドサービスと同様に、不正アクセスやサイバー攻撃による情報漏洩のリスクが完全にゼロであるとは言い切れません。
Notta側でセキュリティ対策を講じていても、利用者自身のパスワード管理の甘さなどが原因でアカウントが乗っ取られるといった危険性も考えられます。
会議の録音などを行う際は、参加者への事前通知や同意取得といった法的な側面も、利用者自身が配慮すべき点です。
AI学習へのデータ利用とユーザーの権利
AIを活用したサービスにおいて、ユーザーデータがAIモデルの学習や改善にどのように利用されるかは、プライバシー保護の観点から非常に重要なポイントです。
Nottaの場合、この点に関していくつかの側面から情報を読み解く必要があります。
Notta株式会社が提供する日本語のプライバシーポリシーには、「音声認識エンジンを提供する第三者のパートナー企業」が、ユーザーの音声データを「音声認識トレーニングに使われることがある」という記述が見られます。
これは、Nottaのサービスを通じて提供された音声データが、直接Nottaではない企業のAI学習に利用される可能性を示唆するものです。
一方で、Nottaの料金プランを紹介する一部情報では、最上位のエンタープライズプランの特典として「AIトレーニングにデータを使用しない」という項目が挙げられていることがあります。
これが公式な条件であれば、他のプラン(無料プランや標準的な有料プラン)ではデータがAI学習に利用される可能性があると解釈できます。
ユーザーは自身の個人情報に対してアクセス、訂正、削除などを要求する権利を有していますが、AI学習へのデータ利用を明確に拒否・停止する(オプトアウトする)ための具体的な手続きについては、現時点ではっきりと示されていません。
データの所有権はユーザーに帰属するとされていますが、サービス提供に必要な範囲でNottaがデータを利用するライセンスを得るという形になっているため、その「範囲」の解釈が鍵となります。
過去のセキュリティインシデントは?
サービスを選定する上で、過去にセキュリティに関する問題がなかったかどうかは気になる点です。
提供されている情報や公開されている資料を調査した範囲では、Notta自身、またはその直接的な関連会社が関与した、公に報告されている重大なデータ漏洩やセキュリティインシデント、あるいは深刻な脆弱性に関する具体的な情報は見当たりませんでした。
Nottaは、脆弱性を管理するためのプログラムや、万が一セキュリティインシデントが発生した場合の対応体制を整備していると説明しています。
過去に重大なインシデントの報告が見られないことは、一定の安心材料にはなるかもしれません。しかしながら、全てのインシデントが公表されるわけではないという一般的な側面も理解しておく必要はあるでしょう。
一部のユーザーレビューでは、データの取り扱いやプライバシーに関する懸念の声が散見されることもありますが、これらが現在のNottaの公式な仕様やポリシーとどの程度合致するのか、あるいは過去のバージョンに関する指摘なのかについては、最新の公式情報と照らし合わせて確認することが求められます。
Notta導入前に確認すべきこと
Nottaの導入を検討する際には、いくつかの重要なポイントを事前に確認しておくことで、より安心してサービスを利用開始できるでしょう。
これらを怠ると、後から「こんなはずではなかった」という事態になりかねません。
まず最も重要なのは、Nottaでどのようなデータを取り扱うのか、その機微性を自社や自身でしっかりと評価することです。
会議の内容や顧客情報など、外部に漏れるべきでない情報を含む場合は特に慎重な判断が求められます。次に、Nottaが提供している利用規約やプライバシーポリシーを隅々まで確認しましょう。
特に、収集されるデータの種類、利用目的、第三者への提供条件、そしてAIモデルの学習に自分のデータが利用される可能性があるのか否か、といった項目は重点的にチェックすべきです。
もしAI学習へのデータ利用を避けたいのであれば、Nottaのサポート窓口に直接問い合わせ、エンタープライズプランなどで提供されている「AI学習へのデータ不使用」オプションの詳細や、他のプランにおける対応状況を確認することが不可欠です。
また、提供されているセキュリティチェックシートがあれば、その内容を自社のセキュリティ基準と照らし合わせて精査し、不明な点は追加で質問することも有効な手段と言えます。
可能であれば無料プランやトライアル期間を利用して、実際の操作感や機能、セキュリティ設定などを体験的に評価することもお勧めします。
ただし、無料プランの場合は機能に大幅な制限があることが多い点に留意が必要です。
Nottaの安全性:総括と主要ポイント
- Nottaは日本法人と海外法人が連携しグローバルに運営される
- 文字起こし精度は最大98.86%と高く、58言語に対応する
- 通信はSSL/TLSで暗号化、保存データはAES-256で保護される
- SOC 2 Type IIやISO 27001といった国際セキュリティ認証を取得している
- GDPRや日本の個人情報保護法など主要データ保護規制への準拠を表明する
- 日本国内企業向けにセキュリティチェックシートが提供される
- サービス提供と改善のためユーザー情報は収集・利用される
- 原則ユーザー同意なく個人情報は第三者に提供されない(業務委託等例外あり)
- データが日本国外の事業者に移転される可能性がプライバシーポリシーに記載される
- 音声データがAIの学習に利用される可能性があり、特に標準プランでは留意が必要だ
- エンタープライズプランではAI学習へのデータ不使用オプションが示唆される
- ユーザーは自身のデータ所有権を持つが、AI学習への明確なオプトアウト手段は不明瞭である
- 公に報告された重大なセキュリティインシデントは現時点で見当たらない
- 導入前に取り扱うデータの機微性を評価し、利用規約の確認が不可欠だ
- AI学習へのデータ利用方針はプランによって異なるため、事前確認が推奨される